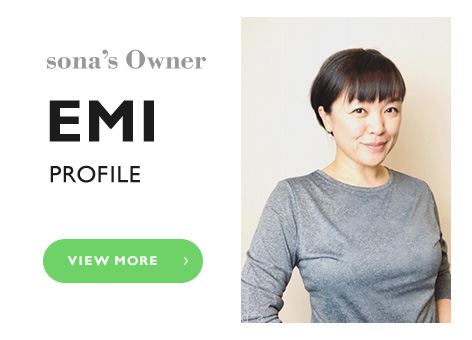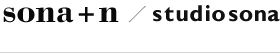いつもお世話になっております( ´ ▽ ` )
我慢。ってなんかネガティブキーワードの様に感じますが、
意外と、よく使いますよね?
特に子育てしてたりすると、子供へ「このくらい我慢しなさい」みたいな・・・
「これで我慢して」とか。
我慢が美徳?の様に使われたりもする。
我慢することが忍耐力であり、我慢することが偉い、立派、の様に。

または、自分自身にも使いますよね。
「今は我慢しておこう」「ここが踏ん張りどころだから我慢しなきゃ」と。
ダイエットで食事制限してる場合も使うこともありますね、「食べるのを我慢我慢、ひたすら我慢」みたいに。
私はヨガの学びの中で、「我慢」の由来を仏教を通して知りました。
以下、ウィキペディアより抜粋です。
我慢(がまん)とは、仏教の煩悩の一つ。
強い自己意識から起こす慢心のこと。 四慢( 増上・卑下・我・邪)の1つ、
また七慢(慢・過・慢過・我・増上・卑劣・邪)の1つ。
仏教では人間を固定的な実体として捉え、自己に執着(しゅうじゃく)することを我執(がしゅう)といい、その我執から、自分を高く見て他人を軽視する心をいった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/我慢
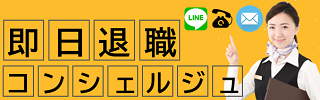
とあります。
要は、自分に執着することから起こる慢心を意味しており、「高慢・自惚れ」と同義語だったそうです。
そこから、「我を張る・強情」などの意味で使われる様になり、
さらに、強情な人は人に弱みを見せまいとふるまう姿、耐え忍ぶ姿。と意味合いが変化していったのです。
今、現在・現代使われてる意味合と違いますね。
語源の由来から考えると、我慢はする物ではないことがわかります。
我慢をすることが素晴らしいことではないことが、本来はたくさんあるんです。
我慢しながら、仕事をする。
これも良くはないことです。
しかし、これまで昔の教育では、生きるために仕方がない、必要だ、我慢してはたらかなければいけない。
定年まで我慢して働かないといけない。

そんな風潮、指導、教え込み、思想だったのではないでしょうか。
しかし結果、その教育はよくないことがわかりました。日本は先進国でありながら、自殺者数が多い国です。
それが事実である限り、「我慢」が必要だと思われてた事柄が、
実は、全く必要じゃないのです。
必要じゃないことに、必要ではない時に「我慢」が使われているからです。
だから自分を俯瞰で観れなくなって、コントロールが利かなくなってしまう。
正常な判断が不可能になってしまう。
我慢しない、避ける、逃げる、遠ざかる・・・
ことの方が必要な場面がたくさんあるはずなのに、
これらが使われることが少ない、使ってはいけないと言う、日本の古い教育が間違っていることに、
そろそろ気づき、教育が変わることを強く望みます。

私も、まだまだ古い考えなところも多くあり、
ひたすら耐えることが自分のためになる、と考えがちです💦
子供にも「今我慢してやらないで、後で大変だよ!」と言ってしまいます・・・
ただ私は、逃げることの決断をする術を身につけました!
頑張りすぎない、我慢しすぎない、嫌なことは嫌、とはっきりとさせることが出来る様になったのです☆
なので、我慢することが素晴らしいとは、今は思わないです!
語源の由来を考えると、高慢な自分や自惚れる自分に執着するなんて、したくはな〜い( ̄▽ ̄;)
慢心な心にはなりたくないですw
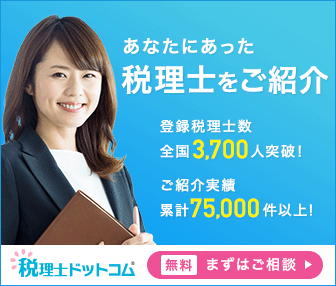
我慢してませんか??
我慢に執着せず、こだわらず、プライドは捨ててください。
逃げ出してください。
我慢する必要はありません。
誰に縛られる必要もありません。
自分の大切な限りある人生の大切な時間を、我慢に充ててはいけません。
自分の道を歩みましょう!!
我慢ではなく、自分を素直に、自分を寛容に、自分の気持ちに答えましょう。
そうすれば、語源であることにはならないです♪
読んでいただいてありがとうございました♡

我慢の使い方。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 1月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||